こんにちは、しゃけです。
今回は【計算編】として、私が会計士の勉強から切り替え、約7ヶ月の勉強期間で簿記論・財務諸表論に一発合格できた、計算問題の具体的な戦略について、その背景にある考え方から、ノートの書き方といった細かなテクニックまで、私の持つすべてをお話しします。
「会計士の勉強をしていたから有利だったんでしょ?」とよく言われます。しかし、そのアドバンテージをもってしても、予備校の模試では
初見で合格点を取れたのは1〜2回だけで、ほとんどが50点台という厳しい現実がありました 。 「このままで本当に受かるのか…」と、何度も心が折れそうになったことを今でも鮮明に覚えています。
しかし、そんな私がなぜ短期で合格できたのか。 それは、才能やひらめきに頼るのではなく、
誰でも真似できる「仕組み」と「徹底した反復」にこだわったからです。特に、「答練」と「ミスノート」を徹底的に活用するという、再現性の高いシンプルな戦術を最後まで貫きました 。
この記事は、単なる勉強法の紹介ではありません。合格というゴールから逆算し、限られた時間の中でどう思考し、どう行動したのか、その全記録です。
第1章:計算学習の「マインドセット編」〜合格るための考え方〜
テクニックの前に、まずその土台となる「考え方」についてお話しします。
なぜ「満点」ではなく「合格点」を目指すのか?〜相対試験の本質を突く〜
簿記論・財務諸表論は、上位何%が合格するという相対評価の試験です 。 これはつまり、
受験生の出来具合によって、問題ごとの配点が変わる可能性があるということです 。
予備校の解答速報では、全ての設問に形式的に配点が振られていますが、私の感覚では、
誰も解けていないような超難問の配点は、限りなく低くなると考えています 。 満点を取るためにそういった難問に時間を費やすのは、費用対効果が著しく低いのです。合格に必要な点数を確保するためには、
配点が高いであろう基礎的な問題を完璧に解ききることが何よりも重要です 。
事実、会計士の勉強で簿記を深く学んでいた私でさえ、答練に出てくる難問に手を出した結果、
8割は間違えていました 。 10問解いたら8問は間違えるような問題に、貴重な試験時間を使うべきではありません。まずは「誰もが解ける問題」を絶対に落とさない。この割り切りが、精神的な安定と合格戦略の要でした。
「ケアレスミス」は最大の敵。その撲滅こそが合格戦略
基礎問題で点を稼ぐ上で、最大の障壁となるのが「ケアレスミス」です。これを撲滅するために、私はミスノート以外に2つの対策を徹底していました。
① 問題文の「全文下線引き」 私は、問題文の読み落としが非常に多発していました 。 これをただの不注意で終わらせず、物理的に対策する必要があると考えました 。
その方法が、
問題文を読みながら、その全文に下線を引くことです 。 特に重要なキーワード(年数、単価、○○法など)は、意識して線を引きます 。 こうすることで、強制的に読むスピードが落ち、一語一句を確実に目で追うことができます。なぜか読み飛ばしてしまう、という方は、何らかの対策を打つべきです 。
② 「頭の中仕訳」と「T勘定フォーム」 以前は、総合問題の全仕訳を紙に書き出して集計していましたが、
3時間半もかかってしまい、すぐにこのやり方を辞めました 。
本番で採用したのは、
頭の中で仕訳を切り、それを巨大なT勘定のフォームに直接転記していく方法です。本当に複雑な仕訳(1つの総合問題に1〜2つ程度)以外は、書き出しません 。
- 準備: まず、解答用紙にBSとPL(必要なら製造原価報告書)の大きなT勘定フォームを2〜3個書きます 。
- 区分: BSの左側には「流・固・投」、右側には「流・固・純」 。PLの左側には「売原・販管・営外費・特損」、右側には「売・営外収・特利」といったように、略称で大きく区分けします 。
- 転記: 問題文を読み、頭の中で仕訳をしたら、勘定科目も「頭文字1文字」などで略記し、該当する区分に直接金額を書き込んでいきます 。
この方法で、仕訳を書く時間を大幅に短縮し、計算と集計に集中することができました。
「わからない問題」との向き合い方〜10分で見切る勇気〜
答練で全く手が出ない「捨て問題」に遭遇することは必ずあります。どれが捨て問題かを見極めるのは、正直なところ「慣れ」の部分が大きいです 。 答練を解く中で、「これは深入りすると危ないな」という感覚を養うしかありません 。
働きながらの勉強で時間もなかったので、私は**「10分程考えて解決しなければ捨てる」**というマイルールを設けていました 。
復習の段階でも、
解答解説を読んでも全く理解できない問題は、潔く捨てます 。 幸い、そんな問題は全答練を通しても10問もありませんでした 。
第2章:計算学習の「教材編」〜何を選び、どう使い倒すか〜
私が「問題集」を使わなかった、たった一つの理由〜信じるべきは答練とテキスト〜
予備校の先生は「解けなかったら問題集に戻れ」と言いますが、私はこれまで
一度も問題集に戻ったことはありません 。 その代わり、必ず**「テキスト」に戻って、その論点の根本的な理解に努めました** 。
なぜなら、会計士の勉強をしていた時代、合格した先輩から聞いた**「大原の答練や予想模試は、全体の論点に触れられるように作られている」**という言葉が、とても印象に残っていたからです 。
良質な答練を完璧にすることこそが、最も効率的で網羅的な学習だと信じていました。
学習の核となる「答練」の選び方と位置づけ〜講師を信じ抜く〜
「どの答練をAランクと判断したか」という質問ですが、答えは非常にシンプルです。 **「講師がAランクと言ったもの」**です 。
予備校の講師は、長年の経験と分析から、その答練の重要度を判断しています。自分で考えるよりも、まずはその道標を信じ抜くことが重要だと考えました。
最高の参考書「ミスノート」の具体的な作り方【詳細解説】
ミスノートは、
ごく普通の大学ノートに作成していました 。
- 物理的な作り方:
- ノート上部の見出し部分に「過去問第10回ー①」のように、どの答練の何ページ目かを記載します 。
- 内容は箇条書きで、間違えた論点を一つずつ書いていきます 。
- 内容の書き方【最重要ポイント】: ミスノートには、**「①正しい知識」と「②その理由」**を必ずセットで書きます 。
(例)その他資本剰余金から出している配当金を、受取配当金(収益)としてしまった場合ミスノート↓
【①正しい知識】 その他資本剰余金の処分で配当がされている場合、投資有価証券の減額とする。 【②その理由】 →その他資本剰余金は「資本金や準備金の減少差額」「自己株式処分差益」からなるもの。 そのような剰余金からの配当は、利益の分配ではなく**「投資の払い戻し」**の性格を持つから。
このように、「なぜそうなるのか」という理由まで書くことで、単なる暗記ではなく、理解を伴った知識として定着させることができます。
復習の質を高める追加ルール: 間違えた箇所を復習する際は、必ずテキストに戻り、その周辺知識も一緒に読むようにしていました 。 そして、少しでも不安に感じた論点は、たとえその問題では間違えていなくても、予防的にミスノートに書いておきます 。 これが知識の穴をなくす上で非常に重要です。
第3章:計算学習の「実践編」〜具体的な勉強サイクル〜
答練のランク別・復習サイクルと周回数の目安〜3周で仕上げる〜
限られた時間の中で、Aランク答練を完璧にするために、私は
平均3回、多くて4回繰り返していました 。
- 常に時間を計る: どんな時でも、必ず本番と同じ2時間のタイマーを設定して解きます 。 これにより、常に本番を意識した緊張感を保つことができます。
- 周回ごとの変化: 2回目ではまだミスは多いですが、3回目になるとミスはかなり少なくなります 。 ここでようやく、知識が定着してきたと実感できます。
「復習の質」を上げる思考法〜周辺知識を芋蔓式に〜
前述の通り、「復習」とは、ただ間違えた問題の解法を確認するだけではありません。
テキストに戻り、その論点の周辺知識も一緒に復習することが、記憶の定着と応用力の向上に繋がります 。 「この論点は、あの論点とこう繋がっているのか」という発見が、理解をさらに深めてくれます。
直前期(6月以降)の過ごし方と勉強時間
私は具体的なスケジュールを細かく立てるタイプではありませんでした 。 しかし、時期に応じた総勉強時間の目安は決めていました。
- 通常期: 平日2時間、休日5時間前後
- 試験1〜2ヶ月前: 平日2時間、休日7時間〜8時間
- 試験休暇中: 1日7時間ほど
この時間を、Aランク答練の周回と、全ミスノートの総復習に充てていました。
以上が、私の計算戦略のすべてです。 特別なことは何もありません。やるべきことを決め、それを信じ、ひたすら繰り返す。 この地道な作業の先に、合格があると信じています。
このやり方が、あなたの「税理士への道」をともに歩むパートナーとなれたら、これ以上嬉しいことはありません。
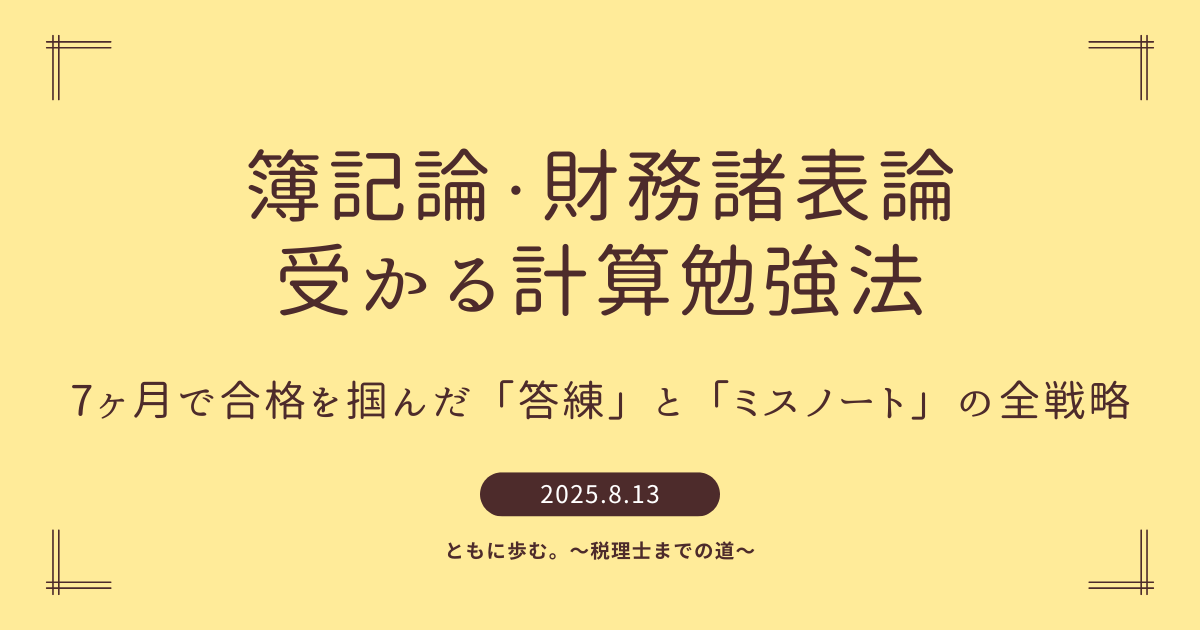
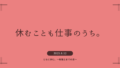
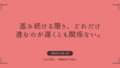
コメント